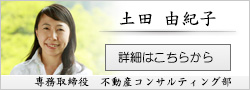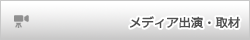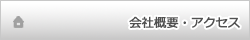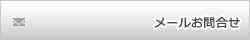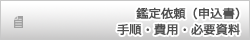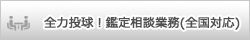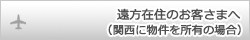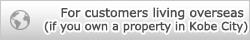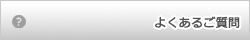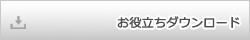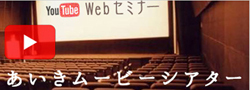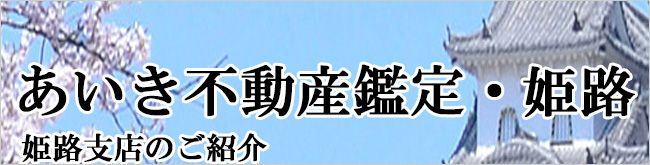業務対応エリア
-
兵庫県全域
神戸市 尼崎市 西宮市
芦屋市 伊丹市 宝塚市
川西市 三田市 明石市
加古川市 高砂市 西脇市
三木市 小野市 加西市
加東市 姫路市 相生市
たつの市 赤穂市 宍粟市
豊岡市 養父市 朝来市
篠山市 丹波市 洲本市
南あわじ市 淡路市 - 東京都
- 大阪府
- 京都府
事業案内
- 税務・会計 不動産鑑定
相続不動産鑑定
広大地評価判定
同族間(役員、法人間等)収益物件の売買 鑑定
同族間(役員、法人間等)収益物件の土地だけ売買 鑑定
同族間(役員、関連会社、親族間等)の建物だけ売買 鑑定
不動産概算取得費計算SOS
等価交換のための不動産鑑定
財務諸表のための価格調査
現物出資のための不動産鑑定
M&A、株価算定のための不動産鑑定
銀行融資額引上げのための不動産鑑定
不動産鑑定相談業務(全国対応)
- 裁判・調停 不動産鑑定
賃料増減 不動産鑑定
遺産分割 不動産鑑定
離婚による財産分与 不動産鑑定
共有物分割 不動産鑑定
立退料 不動産鑑定
他社不動産鑑定書セカンドオピニオン
- 相続・遺産分割 不動産鑑定
不動産概算取得費計算SOS
共有物分割 不動産鑑定
戸建住宅・マンションの不動産鑑定
不動産の仲介
- 建物の不動産鑑定
建物耐用年数の不動産鑑定
建物資産「除却」支援
税金対策と減価償却費計上を目的とした、土地と建物価格の判断のための鑑定
戸建住宅・マンションの不動産鑑定
神戸北野町異人館 伝統的建造物の不動産鑑定 - 価格に関する不動産鑑定
更地の不動産鑑定
更地(広大地)の不動産鑑定
宅地見込地の不動産鑑定
農地・林地・原野の不動産鑑定
借地権・定期借地権の不動産鑑定
底地の不動産鑑定
借地人が買い取る場合の底地の不動産鑑定
- 賃料に関する不動産鑑定
- アセット別の不動産鑑定
病院(クリニック・総合病院・医療モール)の不動産鑑定
老人福祉施設(老人ホーム・グループホーム・サ高住)の不動産鑑定
ホテル(シティ・リゾート・ビジネス・レジャー)・旅館・保養所・別荘の不動産鑑定
工場・倉庫の不動産鑑定
ガソリンスタンドの不動産鑑定
ボウリング場の不動産鑑定
パチンコ店の不動産鑑定
神戸北野町異人館 伝統的建造物の不動産鑑定
- 不動産価格意見書
- 不動産仲介
- 不動産コンサルティング事業
不動産コンサルティング
講演・セミナー
トップページ > 証券化対象不動産鑑定
証券化対象不動産鑑定
私達のサービス
J-REIT、私募REIT、プライベートファンド等のいわゆる証券化対象不動産については
取得時・運用時・リファイナンス時といった様々な場面において、法令上不動産鑑定士による
鑑定評価が必要となります。
証券化鑑定評価実務に精通した鑑定士が中心となって、最新の鑑定技術を駆使し、基準各論第3章、各実務指針、
ガイドライン等を遵守した安心の評価を提供致します。
取得時・運用時・リファイナンス時といった様々な場面において、法令上不動産鑑定士による
鑑定評価が必要となります。
証券化鑑定評価実務に精通した鑑定士が中心となって、最新の鑑定技術を駆使し、基準各論第3章、各実務指針、
ガイドライン等を遵守した安心の評価を提供致します。
証券化対象不動産の鑑定評価の特徴
証券化対象不動産の鑑定評価の特徴についてご説明させていただきます。
まずは、依頼者・関係者の特徴です。
①依頼背景…投信法、資産流動化法、金融商品取引法などの法令上の要請による
②依頼目的…取得・売却時・決算期毎の不動産価格の情報開示のため、投資家の判断材料とするため
③依頼者の属性…資産、つまり投資用不動産の運用業務を行う投資顧問会社や信託銀行、アセットマネジメント会社など
④利害関係者…依頼者だけでなく、広範な投資家に渡る
次に、鑑定評価の業務内容の特徴です。
証券化対象不動産の鑑定評価においては、鑑定評価業務の進め方、採用する手法や査定項目などについても細かく取り決めがあります。
具体的には、不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合に基準とすべき「不動産鑑定評価基準(国土交通省の事務次官通知)」)のうち、「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価(第3章)」を適用しなければなりません。
この第3章は平成19年4月に新設されており、直近では不動産鑑定評価基準は平成26年5月に一部改正がされています。
平成26年5月に改正された不動産鑑定評価基準第3章第1節Ⅱ「不動産鑑定士の責務」については下記の通り記載があります。
特に上記(2)では、証券化の鑑定評価の内容について、採用した資料や鑑定評価額に至るまでのプロセスについて単にその説明責任を負うだけでなく、鑑定評価書を活用する側にとってその内容が把握しやすいよう、評価書の記載方法等まで注意を払うべきと書かれています。
したがって、証券化対象不動産の鑑定評価を担う不動産鑑定業者、担当する不動産鑑定士の責任は相当大きいものであると言えるでしょう。
まずは、依頼者・関係者の特徴です。
①依頼背景…投信法、資産流動化法、金融商品取引法などの法令上の要請による
②依頼目的…取得・売却時・決算期毎の不動産価格の情報開示のため、投資家の判断材料とするため
③依頼者の属性…資産、つまり投資用不動産の運用業務を行う投資顧問会社や信託銀行、アセットマネジメント会社など
④利害関係者…依頼者だけでなく、広範な投資家に渡る
次に、鑑定評価の業務内容の特徴です。
証券化対象不動産の鑑定評価においては、鑑定評価業務の進め方、採用する手法や査定項目などについても細かく取り決めがあります。
具体的には、不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合に基準とすべき「不動産鑑定評価基準(国土交通省の事務次官通知)」)のうち、「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価(第3章)」を適用しなければなりません。
この第3章は平成19年4月に新設されており、直近では不動産鑑定評価基準は平成26年5月に一部改正がされています。
平成26年5月に改正された不動産鑑定評価基準第3章第1節Ⅱ「不動産鑑定士の責務」については下記の通り記載があります。
Ⅱ不動産鑑定士の責務
(1)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価の依頼者(以下単に「依頼者」という。)のみならず広範な投資家等に重大な影響を及ぼすことを考慮するとともに、不動産鑑定評価制度に対する社会的信頼性の確保等について重要な責任を有していることを認識し、証券化対象不動産の鑑定評価の手順について常に最大限の配慮を行いつつ、鑑定評価を行わなければならない。
(2)不動産鑑定士は、証券化対象不動産の鑑定評価を行う場合にあっては、証券化対象不動産の証券化等が円滑に行われるよう配慮し、鑑定評価に係る資料及び手順等を依頼者に説明し、理解を深め、かつ協力を得るものとする。
また、証券化対象不動産の鑑定評価書については、依頼者及び証券化対象不動産に係る利害関係者その他の者がその内容を容易に把握・比較することができるようにするため、鑑定評価報告書の記載方法等を工夫し、及び鑑定評価に活用した資料等を明示することができるようにするなど説明責任が十分に果たされるものとしなければならない。
(3)証券化対象不動産の鑑定評価を複数の不動産鑑定士が共同して行う場合にあっては、それぞれの不動産鑑定士の役割を明確にした上で、常に鑑定評価業務全体の情報を共有するなど密接かつ十分な連携の下、すべての不動産鑑定士が一体となって鑑定評価の業務を遂行しなければならない。
特に上記(2)では、証券化の鑑定評価の内容について、採用した資料や鑑定評価額に至るまでのプロセスについて単にその説明責任を負うだけでなく、鑑定評価書を活用する側にとってその内容が把握しやすいよう、評価書の記載方法等まで注意を払うべきと書かれています。
したがって、証券化対象不動産の鑑定評価を担う不動産鑑定業者、担当する不動産鑑定士の責任は相当大きいものであると言えるでしょう。
証券化評価の法令(随時更新中)
病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン 平成27年6月
国土交通省が「病院不動産を対象とするリートに係るガイドライン」を公表した。証券化対象不動産の鑑定評価に関する実務指針 平成26年11月
日本不動産鑑定士協会連合会が「証券化対象不動産の鑑定評価に関する実務指針」を発表した。